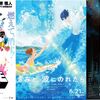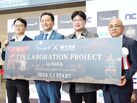【平成後の世界のためのリ・アニメイト】第7回 ウイルス禍の時代に考える「十三機兵防衛圏」(後編)
「母性のディストピア」からの脱出へ──グレートマザー・千尋との交渉
では、みずからの身体を取り戻し、新たな惑星の大地に立とうとする13人の子らの通過儀礼は、どのようになされたのか。
彼らの抗いの対象となる箱舟世界の母性のディストピアの根源が、グレートマザーとしての千尋(子供)≒2188年の森村博士であり、その計画を狂わせるDコードを投入した(そしてメタ的には綾波レイの造形を踏襲した)2188年の東雲諒子である。多くの神話における太母の元型と同様、子らを育み守る存在としての「良き母」と、自立を阻む「荒ぶる母」としての二側面を、それぞれが象徴している。
そして現代における母性のメタファーとは、それなくしては生きられない環境システムのことである以上、近代確立期のような「父殺し」「神殺し」ならぬ「母殺し」を完遂すればいいという単純な構造にはならない。だからこそ、沖野や426がなしえたのは、古典的なディストピア抵抗SFのようなシステムそのものの破壊や革命ではなく、あくまでも箱舟プログラム本体を流用してのハッキングであり、ゲームの書き換えだったのである。
そして書き換えられたゲームである「崩壊編」に倒すべきラスボスの類はなく、郷登の指揮する作戦は、千尋に殺された森村(先生)が企図していたイージス作戦とほとんど変わるところはない。文字通り波のように押し寄せるダイモスの群れから、街の各エリアにある標的ターミナルを死守し、イージスシステムが発動してエリア内の敵を一掃できるようになるまで耐え忍ぶという、時間稼ぎのタワーディフェンスの繰り返しのみだ。
ただし、すべてのターミナルのイージスが発動すると中枢のユニバーサルコントロールとのリンクが遮断されて仮想世界に取り残されてしまうため、最後のターミナルのイージスだけは起動するわけにはいかない。そこまで稼いでいる時間を使って、現実世界の衛星軌道上にいる因幡深雪が、Dコードの影響を受けないリンクを司令船から迂回接続することで中枢に現状が異常事態であることを認識させ、保育器に眠る15人を緊急覚醒させることが、PCたちにとっての最終的な勝利条件であると提示される。
言うなれば「荒ぶる母」を正気に立ち返らせ、正しく子離れさせること。それがこの物語が見出した、ロボットアニメ史にビルドゥングスロマンを取り戻すための具体的道筋であった。
しかし、このプランを子らの力だけで達成できるようには描かなかったのが、本作のクライマックスのミソだ。因幡によるハッキング処理が終了間際になった段階で、衛星軌道を周回する司令船が交信可能範囲を外れてしまい、戻ってくるまでにさらに半日以上の時間を要するという絶望的な状況が訪れる。通信が切れるまで士気を鼓舞するため軌道上のアイドルが持ち歌「渚のバカンス」を歌うといった「マクロス」オマージュの演出を挟みながら、事態を打開するためのラストピースは、最後の登場人物に託されることになる。地球人類の絶滅に責任を持ち、この状況をもたらした張本人・千尋である。
「追想編」郷登編のシナリオで、彼女は今周の15人が新天地に降り立つに値する人類であるかどうか、創造主目線で現人類代表の郷登と知恵比べがてらの賭けをするという立場を採っている。そしてロジカルな推理で箱舟計画の真相や森村殺害の犯人、さらに自分の正体を言い当ててみせた郷登が、欲望まみれの素顔をさらけ出してノーガードの「お願い」をしてみせる残念なイケメン力にほだされ、彼らのために上級IDで2つの助力をすることになる。ひとつは、セクター4の(しょせんAI制御された擬似人格にすぎない)沢渡美和子たち120万人のモブ市民全員をセクター3へ退避させること。もうひとつが、惑星の監視衛星を中継地点までに移動させて因幡との交信を復活させること。
これが決め手となり、最後のターミナルに殺到するダイモス群のインフレからシステムを死守しつつ、15人の肉体をポッド外で生命維持できる状態にする緊急脱出処理が成立。地球から1200光年離れたRS13星系のアルファ惑星にて、人類再生の永い通過儀礼が、ようやく完結する。
ここでは打倒や超克ではなく、交渉と説得によって、ポスト・エヴァのロボットアニメが陥った母性のディストピアからの脱出路が示されたのである。
SFと同時代のジュヴナイル表現のあいだ──そしてポスト・ウイルスの想像力へ
以上が、この物語で描かれた事件の真相と解決の全貌だ。時系列を複雑に前後させながら語られていく「追想編」と「崩壊編」の往復で、初見プレイ時には理解しきれなかった筋立てを、改めて「究明編」のイベントアーカイブで順を追って読み直してみた際の、すべてが緻密に繋がって腑に落ちていくカタルシスには、格別なものがある。
本作をして、ADVを中心とするストーリーゲーム分野のみならず、近年の物語コンテンツの最高峰と称する声が少なからず聞かれたことにも、深く納得する。
ただし改めてこうして振り返ると、プロットや道具立ての複雑さに比して、その着地点はいささか拍子抜けではあったかもしれない。要するに、2188年の地球人類が計画した播種計画が、最終的に本来のプログラム通りに修正されただけと言えばだけの話だ。オリジナル東雲諒子のセカイ系的な情念による妨害がなければ、このプロセスにはなんら通過儀礼的な試練の発生のしようもなかったのである。
もちろん、悠久の時を隔てての恒星間移民をテーマにしたSFで、計画のトラブルとその対処を描くというプロットはお約束の類型だから、そのこと自体は問題ではない。ただ、本作の場合はそうしたシチュエーションベースのSF的な思考実験性よりも、やはりロボットアニメ的な13人のPCたちのジュヴナイル群像としての比重が大きいことは明らかである。その観点からすれば、ここまでたどってきたように、確かに歴史を徹底的に棚卸しすることで、ポスト・エヴァの袋小路からの脱却という意味では理知的な模範解答が示されていたものの、13人(あるいは15人)の生き様から時代を切り拓く新しい価値観やイメージが示せたかという点では、そこまでの到達には至らなかったのではないだろうか。
たとえば、箱舟計画の目的性への疑義や、惑星植民でどんな世界を築くのかの路線対立など、真相を知ったうえでの主体的な選択や決断によって、既定路線ではない未来像が左右しうる状況設定があれば、「実は惑星植民の準備段階だった」という真相を、単なるプロット上のどんでん返しインパクトに留めず、ジュヴナイル文芸としての〈成熟〉像の更新に結びつけていくことができたかもしれない。
それから、本作の状況設定の突き詰めで物足りなく思うのは、やはり「人類がそこからやり直すべき5つの時代」というセクター併存の秀逸なアイデアを、いまひとつ生かしきれていなかったことだ。
「メガゾーン23」から想を得たこの道具立てが、元よりディレクターの神谷盛治にとって最も思い入れがあって描きやすい1980年代(セクター4)を物語の最終防衛線として特権化するための方便だったのは仕方ないにせよ、2100年代(セクター1)・2060年代(セクター2)・2020年代(セクター3)が総じて「未来」枠のくくりで、それぞれの時代の空気感やそこで育ったキャラたちの人生観の違いとして表現するまでには至らなかったように見えたのは残念に思う(唯一、現代っ子としての空気感をまとう如月兎美のネット動画の「歌い手」設定はあるが、因幡深雪の1980年代アイドル設定に落とし込むための付随でしかない点は弱い)。
一方で、1940年代(セクター5)があることは日本の特撮・ロボットアニメ史を批評的に参照するうえでは本稿で論じたように非常に重要だが、わざわざ戦時の状況まで再現している居住区に2188年の三浦慶太郎のような人々が住みたがるという設定には、かなり無理があるだろう。そもそも5つの過去年代が、2188年の箱舟計画の立案者たちにとってどのような可能性を持つ時代として評価され、その仮想体験が惑星植民の段階でどう機能するはずだったのかのプロセスが、もうすこし語られてもよかった(たとえば、それぞれの時代の仮想現実を経験した15人が惑星に降り立つ際、各自が経験した時代からの続きの「理想の時代」を最先端の自動工場テクノロジーで惑星を5分割して作り直すことが本来の計画であった……とか)。
そのあたりのもっと相対的な歴史観やSF的シミュレーションの下支えがなければ、「やっぱり1980年代ニッポンは最高だった!」という、令和日本の随所に蔓延している内向きの気分の再生産に、結局のところ本作も加担するものにしかならないからである。
おそらく、宇宙時代でありながらなぜか(欧米圏のグローバルコンテンツでポリティカルコレクトネスとされているような多人種・多民族共存型ではなく)乗組員全員が日本人である「ヤマト」型の文化コードの枠内での作品制作を自覚的に選んだであろう本作は、平成という30年の入り組んだループから抜け出して、改めて21世紀的な情報環境下における成熟像を希求する日本人の現在地の自画像にはなっている(日本流の「擬似ポレコレ」である沖野と比治山のゲイカップルにだけは重要な役割を与えている点も含めて)。が、その先の新天地をどう生きるかまでのビジョン提示は、本作のエンディングには見出すことができない。
だからそう、「十三機兵」は2D表現を駆使したドメスティックな諸ゲームメカニクスのハイブリッドと、特撮・SFロボットアニメの徹底的な棚卸しを通じて、戦後から2010年代までの日本的想像力を総ざらいし、1980年代を頂点とする繁栄の時代の「終わり」を見事すぎるほどに飾る作品ではあったが、2020年代から先の未来を(射程に捉えてはいながらも)展望する作品ではなかったというのが、筆者の最終評価である。
ただ、そうしたクラシックな想像力の点検を通じて、奇しくも新型コロナウイルス禍で引きこもりとテレワークを強いられている2020年上半期現在の人類の姿と、(ナノマシン戦争とパンデミックによる絶滅を経て)保育器の中で仮想空間での擬似身体を操りながら成熟の時を夢見ている本作の少年たちの姿が重なり合って見えるのは、怪我の功名のようなものだろう。
してみれば、如月や薬師寺の生きるセクター3として2020年代が人類やり直しの時期に選ばれたのは、第二次世界大戦の焼け跡からの再起をはかる1940年代、グローバル資本主義の加速と冷戦の終結を控える1980年代に続く転機として、このコロナ危機を経た世界が大きな再出発の可能性を見せていたから、ということになる。
願わくば、「十三機兵」における温故知新がそうした再生可能性の予言だったと思えるよう、私たちもアニメやゲームを含む文化の歴史という保育器の中で、やがて再び外の現実をつくり変えるための想像力を研ぎ澄ませていくことにしたい。
■筆者紹介
中川大地
評論家/編集者。批評誌「PLANETS」副編集長。明治大学野生の科学研究所研究員。文化庁メディア芸術祭エンターテインメント部門審査委員(第21〜23 回)。ゲーム、アニメ、ドラマ等のカルチャーを中心に、現代思想や都市論、人類学、生命科学、情報技術等を渉猟して現実と虚構を架橋する各種評論等を執筆。著書に『東京スカイツリー論』『現代ゲーム全史』、共編著に『あまちゃんメモリーズ』『ゲームする人類』『ゲーム学の新時代』など。
関連ゲーム
ログイン/会員登録をしてこのニュースにコメントしよう!
※記事中に記載の税込価格については記事掲載時のものとなります。税率の変更にともない、変更される場合がありますのでご注意ください。
- 【2024】4月オススメオンラインゲーム[PR]
-

ストリートファイター:デュエル
2024年3月27日配信開始!人気のアーケードゲーム「ウルトラストリートファイターIV」をベースにしたRPG!
-
BLUE PROTOCOL(ブループロトコル)
バンダイナムコオンラインとバンダイナムコスタジオの共同プロジェクトチーム「PROJECT SKY BLUE」による、オンラインアクションRPG!
-
放置少女 for ブラウザ
操作は超簡単、フルオートバトルで放置プレイ。絆を紡いで物語を進めよう! 三国志の世界観を踏襲!
-
ファンタシースターオンライン2ニュージェネシス
セガが開発・運営する基本プレイ無料のオンラインRPG。オンラインRPGの礎を築いた「PSO」シリーズの最新作であり正統後継作品!
-

金色のガッシュベル!! 永遠の絆の仲間たち
テレビアニメ「金色のガッシュベル!!」をベースにしたゲームアプリ!好きな魔物でチームを編成して術や技を繰り出しながら敵を倒して物語を進めよう!